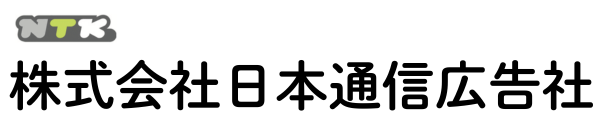「面白い」の裏にある「難しいけど楽しい」創作の世界
先日、京都府福知山市でこんなセミナーの講師をしてきました。
「寄席芸鑑賞講座~落語の仕組み(ふりから落ちまで)~」
日時:2025年9月11日13:30~15:30
場所:京都府福知山市
主催:京都社会人大学校 北近畿校

落語台本がどのように作られているか、考えたことはありますか?
今回の講座では、落語台本の書き方と、その元になる「落語の構成」についてお話しました。
参加者の声をもとに、受講生の3つの発見をご紹介します。
受講生の発見1:「笑い」の裏側にある、想像以上の「難しさ」
参加者の感想では、新作落語の台本作りが想像以上に難しいという声が多く寄せられました。落語家さんが演じる落語を聞いていると、とても軽やかで自然と笑ってしまうことがあると思います。この自然と笑ってしまう裏には、観客を惹きつけ、見事なオチに繋げる台本がベースにありますが、この台本作りには技術(コツ)が必要です。特に、ある参加者のこの言葉が印象的でした。 「落語台本の作り方が、こんなに難しいとは思っていませんでした。」 この作り手の「難しさ」は、落語台本を考える側になってはじめて気付くことだと思います。普段、何気なく楽しんでいる話の中にも、緻密な工夫や技術が隠されていることに気付いていただけたようです。
受講生の発見2:一番の学びは「手を動かす楽しさ」
講座の中で特に好評だったのは、「小噺」を実際に作るワークショップです。「小噺を作るのが面白かった」「完成した小噺を皆に聞いてもらうのが楽しかった」といった感想が多く寄せられました。 知識として聞くだけでなく、手を動かして創作することが貴重な体験であることを実感していただけたようです。私が担当する講座では、一方的に講義内容をお話するだけではなく、参加型にして、参加者の方に考えてもらったり、手を動かしたりしてもらうことをいつも大事にしています。
受講生の発見3:作り手の視点を知ると、鑑賞がもっと面白くなる
「知らなかった落語台本作りのことを知れて、大変面白く、さらに落語に興味が湧きました」という感想をいただきました。 作り手の視点を得ることは、鑑賞体験そのものを豊かにします。落語台本の基本的な構成や特徴、そして想像力の重要性といった台本作りの基礎を学ぶことで、参加者の方にとっては落語を全く新しい視点から見つめ直す機会となったのではないかと思います。
所 感
今回初めて福知山で落語台本に関する講座を担当しました。受講生はシニアの世代の方が多く、年を重ねても学びたいという姿勢や意欲に大変刺激を受けました。「落語台本の作り方を学ぶ」という初めてのチャレンジに難しさはあったと思いますが、終了後も「おもしろかった」「難しかったけど、楽しかった」「さらに落語に興味が沸いた」「こんな丁寧にこの講座の準備をしてくれてありがとう」など、様々な感想を言いに来てくださって本当に嬉しかったです。 今回はお招きいただきありがとうございました。 講座内容はご要望に応じてカスタマイズ可能ですので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。